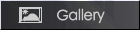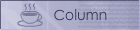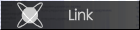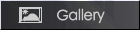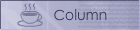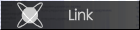#09.. ストーリーテラー #09.. ストーリーテラー |
| Update : 2005/07/02 15:21:00 |
昔、何かで読んだ物語。あるいはどこかで誰かに聞いた物語。
古い物語は内容に矛盾があったり、理不尽であったりする。しかし、そこが面白かったりすることもある。
印象に残ったものや、有名なものでも、その細部までは記憶に残っていないことが多い。
それに人によって、書物によって内容が微妙に違う場合が多い。
私は調べられるものは調べて、無理なものはかすかな記憶で補うことによって、幾つかの物語をまとめることを試みた。
小さい頃気付かなかったことや思わなかったこと、違う感想を抱いた思い出と比較すると新たなる発見があるかもしれない。
七夕
昔、ある村にミケランという若者が住んでおりました。彼は農夫でした。
ある日、ミケランは畑仕事の帰り道、木の枝にとても美しい衣を見つけました。
その衣が欲しくなったミケランは、籠に入れて持って帰ろうとしました。すると、
「あ、もし・・・」と何者かの呼ぶ声がしました。
「誰? 俺に何か用?」
「どうか、私の羽衣を返して下さい。それがないと私は天に帰ることができません」
「羽衣?!」ミケランはびっくりしました。
「実は、私は天女なのです」
「うそーん」
「本当です。羽衣がないと困るのです」
「は、羽衣なんて・・・俺は知らんぞ」ミケランは、いまさら自分が羽衣を隠したとは言えず、知らない振りをしました。
そして、その後ろめたさと同情からその天女を世話しました。
ミケランと七夕は皆が羨むほどの仲の良い夫婦となり、楽しい日々を過ごしました。
ところが、数年たったある日のこと。
ミケランが出かけた後、七夕はいつものように機織をしていました。すると、一羽の鳩が天井裏から見覚えのある衣を引っ張り出しました。
それは、七夕の羽衣でした。七夕は天に帰らねばなりません。
日が暮れて帰ってきたミケランは、羽衣を纏った七夕を見て全てを悟りました。
七夕は天に昇りながら言いました。
「ミケラン、もしも私のことが恋しいなら、わらじを千足あんで、庭に埋めてください。そうすれば、再びお会いできるでしょう。・・・きっと、そうしてくださいね」
ミケランは、次の日から早速わらじを作り始めました。昼も夜もずっとわらじを作り続けました。
そして、とうとうわらじ千足が完成して庭に埋めました。すると、地面から竹が生えてきました。ミケランは竹に登り、天を目指しました。
ついに、二人は喜びの再会を果たしたのです。二人は感動のあまり、声も出ませんでした。
そのとき、杖を持った老人が現れました。
「あ、おとうさん・・・」それは七夕の父でした。
「誰じゃ! その男は」
「私の夫、ミケランです」
「じゃあ、ワシは誰じゃ?」
「あなたは私の父です」
「で、おぬしは下界で何をしておったのだ?」
「畑仕事です」
七夕の父は、娘が下界の人間と結婚したのが気に入らず、ミケランに種を撒くよう命じました。
しかし、ミケランが畑に種を撒き終わると、こう言いました。
「誰が畑に種を撒けと言った? 向こうの田んぼに撒け」
ミケランはがっかりしました。その様子を見ていた七夕は、鳩を使って畑の種を田に撒き直すのを手伝いました。
「うーむ、なかなかやりおるわい」七夕の父は忌々しそうに次の仕事を言いつけました。
そのうち、嫌になってミケランが逃げ出すだろうと考えたのです。
次の仕事は、
「三日三晩、瓜畑の見張りをせよ」というものでした。
これは大変な仕事です。とても喉が渇きます。
「ミケラン、喉が渇いても決して瓜を食べてはいけませんよ。気をつけて下さい」七夕はミケランに注意しましたが、ミケランはその意味がよくわかりませんでした。
喉が渇いたミケランは、とうとう我慢できずに一つだけなら、と瓜に手を出しました。
すると、瓜の中からどっと水が溢れ出しミケランを押し流してしまったのです。
「ミケラン!」
「七夕!」
離れ離れになった二人は、天の川を挟んで二つの星となりました。それが牽牛星と織女星です。
二人は一年に一度だけ会うことを許されました。
それが、七月七日の七夕の日です。
鶯長者
昔、ある小さな村に一人の若者が住んでいました。彼は、珍しい品物を色々な街に売り歩く商人でした。
ある日、少し遠くの街に商売に行こうと思った若者は、梅の咲く雑木林を通りました。
そこは梅の香りと、美しい鶯の鳴き声に包まれた、心安らぐ場所でした。
若者は、梅の木のそばに荷物を下ろして休憩しているうちに、いつの間にか眠ってしまいました。
目を覚ました男が林を進むと、家が一軒ありました。
そこには若い女性がいました。
男は珍しい品々を女に譲り、すっかり気に入られました。
しばらく滞在するようにすすめられ、二、三日くらいならと思っていた男は、いつの間にか何日も女の家に留まっていました。
そればかりか、ずっとここにいても良い、とさえ思うようになりました。そのことを女に告げると、それが良いという快い返事が返ってきました。
ある朝、女は出かける前に男に忠告しました。
「少し出かけてきますが、決して箪笥の引き出しを開けてはなりません。いいですね」
もちろん、初めは箪笥の引き出しなど開けるつもりはありませんでしたが、開けるなといわれて、男はどうしても開けてみたくなったのです。
開けてみて、男はびっくりしました。そこには、野や山が広がっていたのです。
そして大勢の小人が、ある者は田を耕し、ある者は洗濯をするなどそれぞれの生活を営んでいるのでした。
その村に見覚えのあった男は、そこが何処なのか必死で思い出そうとしました。
「見てしまったのですね・・・」
はっとして、入り口に立つ女の悲しげな表情を見た途端、男の意識は急速に薄れていきました。
目を覚ました若者は、自分が林の中にいることに気付きました。
若者はぼんやりと、聞こえなくなった鶯の鳴き声をじっと待ち続けました。
|
 |
|
 |
|